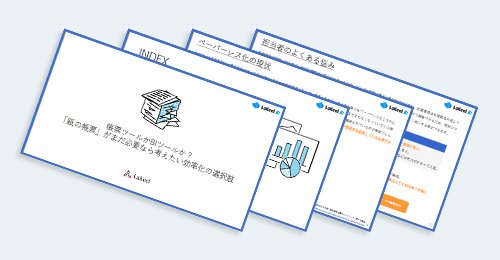データ活用におけるツール選びのポイントとは?
「IoT」「ビッグデータ」などのワードの広がりとともに、データ活用の勢いは加速しています。自社でも取り組みたいとお考えの方も多いと思いますが、それには適切なツール選びが重要となります。ここでは、データ活用を行うメリットと分析ツール選びのポイントについてご紹介いたします。
データ「活用」のために必要な視点
Excelなどのツールを使ったデータ集計やグラフ化作業を日常的に行っている方も多いでしょう。日次・週次・月次などあらゆるタイミングで、データを集計したりレポート化して提出したりするシーンは発生します。しかし、ただデータを集計しグラフ等で可視化するだけでは、真のデータ活用とは言えません。大切なのは、「そのデータから何を読み取り、次にどんなアクションを起こすか」です。つまりデータ活用とは、「集計したデータから値の上昇・下降などの変化に気づき、その要因や法則を突き止めた上で、次の戦略を立てる」ことです。
データを活用するメリットとは?
単なるデータ集計や可視化だけでは、過去を振り返る・結果を確認することがメインとなってしまいがちです。データを活用する視点を持つと、その結果を次に生かすことにフォーカスするようになります。社員全員がデータ活用の意識を持つようになれば、経験則や勘に頼ったアクションではなく、データに基づいた「戦略」を立てて行動や検証ができる(PDCAサイクルを回せる)組織になるため、ゆくゆくは会社全体の生産性が大きく向上していくでしょう。
これだけは外せない!データ活用におけるツール選びのポイント
データを活用するためには、適切なツールを使ったデータ集計や分析を行う必要があります。データ分析業務に使う主なツールとしては、BIツールやExcelなどが挙げられます。少量データの分析であればExcelでも十分対応可能ですが、データ活用を本格的に行う場合は、データの破損や消失のリスクを防ぎ「企業の資産」として管理していく視点も含め、BIツールを導入した方が良いでしょう。BIツールの選定を行うにあたっては、以下のポイントを必ず確認しましょう。
①扱うデータ量に適したスペックであること
活用したいデータをあらかじめ選定した上で、そのデータ量に適したBIツールを選定しましょう。IoTデータなどのビッグデータを想定している場合は、ツールによって集計速度が大幅に異なる可能性もあるため、大量データの高速処理を得意とするBIツールを選定した方が良いでしょう。しかしそこまでデータ量が多くない場合には、スピードよりも操作性やコストに比重を置いてツールを選ぶという方法もあります。いずれにしても、「どんなデータを使うのか」「データ量はどれくらいか」をきちんと想定し、それに適したツールを選びましょう。
②データを多角的に見られること
単なる集計や可視化ではなく「活用」の視点を持った場合、データをさまざまな切り口で見られる機能は必須となります。同じデータでも「年度別や支社別に見たい」「特定の条件に値する日だけ抽出したい」「製品Aだけの明細データが見たい」など、分析を進めるうちにさまざまな要望が上がってくるようになります。このようにデータを多角的に分析するには、集計されたデータを一段階ずつ掘り下げて確認する「ドリルダウン機能」や、データの項目を自由に入れ替えできる「アドホック機能」などが必要となりますので、選定時には必ず確認しましょう。
③複数のデータを集計・統合できること
データ活用を行うにあたり、単一のシステム等からのデータのみではなく、複数の異なるデータを掛け合わせて分析したいという要望が上がることも多くあります。「売上データと気象データ」「財務データと顧客データ」など、複数のデータファイルやシステムなどのデータを統合して分析するシーンが必ずと言って良いほど出てきます。そのため、複数システムのデータを集計したり、特定の値をキーにしてデータを統合したりできる機能がついていることが望ましいでしょう。中でも、基幹システムや情報系システム、Excelファイルなどさまざまな形式のデータを集計できる「ETL機能」がついていると大変便利です。
以上がデータ活用におけるツール選びのポイントとなります。データ活用への取り組みを全社的に行うことで、企業の更なる発展や生産性向上を目指しましょう。
DOCUMENT