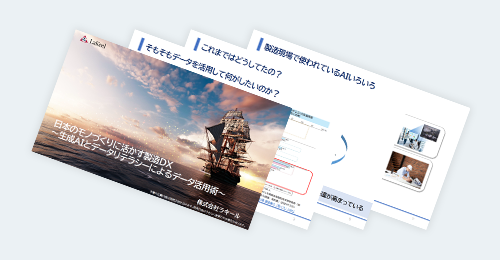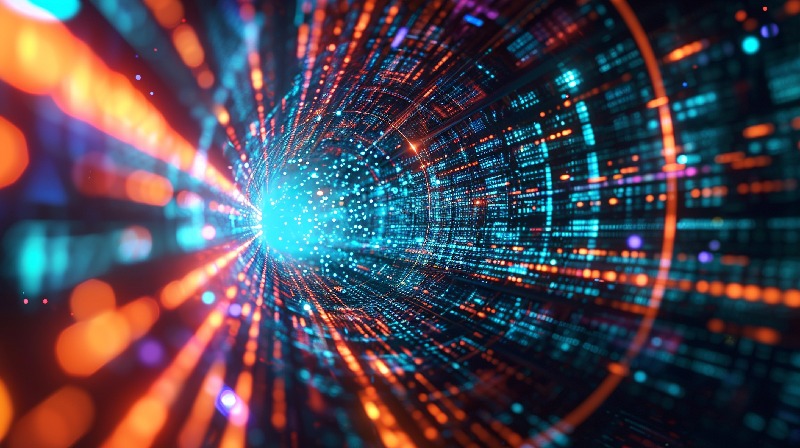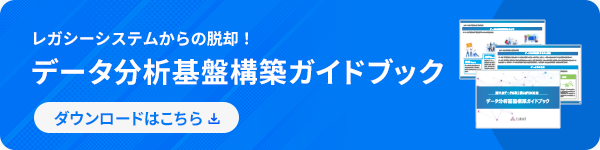
データマネジメントとは?効率的に進めるためのポイントを解説!
データを収集して分析し、可視化した上で社内の各種意思決定に役立てることは、現代のビジネスにおいては当たり前のこととなってきました。そのような中、日々、蓄積されていくデータをいかに効率的かつスピーディーに利用することができるかという「管理」の点にも注力する必要があるでしょう。
今回は、データ管理を担うデータマネジメントについてご紹介します。求められる背景やメリット、効率的に進める方法を見ていきましょう。
データマネジメントとは?
データマネジメントとは、端的に言えば「データの管理」のことを指します。これには、主にデータの登録・更新・活用における全体管理の意味が含まれます。
データマネジメントを効果的に行うためには、データを蓄積するための仕組みを構築し、検索性を向上させること、そして日々の運用を維持することが必要です。
さらにデータは構造化してより効率的に利活用ができるように可視化し、整備しておく必要があります。また、データの内容や重要性に応じて、それぞれのデータに適切なセキュリティ対策を施すことも、データマネジメントの重要な部分です。
◆データマネジメントの11の構成要素
データマネジメントの範囲は非常に幅広いことから、データの専門家によって11の領域に分けられたものが利用されることがあります。
非営利団体DAMA(Data Management Association International)によるデータマネジメントに関する知識をまとめた書籍「DMBOK(Data Management Body Of Knowledge)」では、データマネジメントは次の11の知識領域に分かれることが紹介されています。
| データガバナンス | 組織のデータを適切に管理・活用するために、方針・ルール・標準を定め、役割と責任を明確化し、継続的に維持・実行していくための組織的な活動全般を指します。 |
|---|---|
| データアーキテクチャ | 組織のデータ資産を体系的に構造化し、標準化・最適化された設計として定義するものです。データの生成、流通、管理、活用の全体像を明らかにし、将来的な拡張性や相互運用性も考慮した設計をするための考え方です。 |
| データモデリングと デザイン |
ビジネス要件を基に、データの構造や関連性を分析し、データベースなどで実現可能な論理的・物理的な形式に設計するプロセスです。 |
| データストレージと オペレーション |
データのライフサイクル全体にわたり、安全かつ効率的に保管・運用する活動です。バックアップや障害復旧に加えて、パフォーマンス監視、容量管理、アーカイブ管理なども含まれます。 |
| データセキュリティ | データへの不正なアクセス、改ざん、漏洩などを防ぎ、データの機密性、完全性、可用性を確保するための方針や技術的対策のことです。 |
| データ統合と相互運用性 | 組織内外の異なるシステムに散在するデータを連携・統合し、システム間で円滑にデータを交換・利用可能にするための技術やプロセスです。 |
| ドキュメントと コンテンツ管理 |
契約書や報告書などの非構造化データ(ドキュメント、画像、動画など)を効率的に保管、検索、共有、廃棄するための一連の管理手法です。 |
| 参照データとマスタデータ | 顧客、製品といったビジネスの核となる実体を表す「マスタデータ」と、都道府県コードなどの分類に使われる「参照データ」を正確かつ一貫性のある形で管理することです。 |
| データウェアハウスと ビジネスインテリジェンス |
組織の意思決定を支援するために、様々なシステムからデータを集めて蓄積(データウェアハウス)し、分析・可視化して洞察を得る(ビジネスインテリジェンス)ための一連の活動です。 |
| メタデータ管理 | データの意味、出所、フォーマット、関連性といった付帯情報(メタデータ)を管理することで、組織内のデータ検索や理解を容易にすることです。 |
| データ品質管理 | データの正確性、完全性、一貫性などを維持・向上させることで、データがビジネス要件を満たし、信頼できる状態を保つための継続的な活動です。 |
例を挙げると、データマネジメントを統制するための活動である「データガバナンス」を中心として、まずはデータの構造化や管理についての計画と設計を戦略的に行う「データアーキテクチャ」に取り組みます。また「データモデリングとデザイン」ではデータベースなどのデータ蓄積の仕組みを構築し、「データストレージとオペレーション」では、データを効率的に格納して必要な操作を行うための技術とプロセスを管理します。
さらに、「データセキュリティ」においてはセキュリティポリシーの制定や認証管理などを行い、「データ統合と相互運用性」では各種データを統合するための基盤作りを行います。
データマネジメントが求められる背景
近年、企業におけるデータマネジメント、すなわち社内データの管理が重要視されていますが、その背景には主に次の理由が挙げられます。
◆データ量・種類の増加
近年、デジタル化が急速に進んでおり、社内にも各種システムが数多く存在し、連携しながら多様なデータを取り扱うようになっています。データ量と種類は共に膨大に増え続け、日々蓄積されている状況です。
データが社内のあちこちに散在する状態では、いずれ混乱が生じることは明らかです。データマネジメントの領域のうち、データモデリングとデザインがあるように、データ蓄積の仕組み構築と維持は重要なものとなっています。
◆データを収集して蓄積しているにもかかわらず、適切に活用できていない課題への対応
データの蓄積に関する体制は整っているという場合も、次の「活用」段階に課題があることもあります。データはいくら蓄積されていても、活用できなければ宝の持ち腐れとなってしまいます。いかに活用するかという課題に多くの企業が直面していることも、データマネジメントを適切に全社的な取り組みとして実施していくことが求められている背景といえます。
◆DX推進基盤づくりとして
DXとは、近年のビジネスにおける厳しい環境変化を背景として、企業が競争力を培い、維持するためにデータとデジタル技術を活用して、顧客ニーズや社会ニーズに応え、製品・サービス・ビジネスモデルなどを変革することを指します。さらに業務プロセスや企業文化・風土を変革することで、競争上の優位性を確立することもその範囲に含まれます。
そのため、データを管理しながら適切にデータを活用できるようにして、ビジネスにつなげるデータマネジメントは、DX推進において欠かせない活動といえます。
◆データガバナンス実行の必要性
データガバナンスとはデータの統制を行うことでデータマネジメントの効果の最大化と、リスクの最小化を実現するための取り組みです。
具体的にはデータマネジメントの方針、評価、監視を担います。データを取り扱うケースが増えている昨今、企業としてデータ活用に潜むセキュリティやプライバシー保護のリスクを低減する必要性が高まっています。データガバナンスを推進するためにも、日々のデータマネジメントは欠かせないものとなっています。
データマネジメントのメリット
データマネジメントを推進することにより、次のようなメリットが得られます。
◆全社データ統合・活用促進の土台ができる
データマネジメントを適切に行うことで、社内に散在しており、整理されていないデータを統合し、活用するための基盤作りが実現します。データ活用は昨今の変化の激しいビジネス環境において競争の優位性を保つためには欠かせない取り組みです。
データマネジメント体制を整えることによってデータ整理の土台が作られることは、データ活用の基本的な仕組み構築につながります。
◆データ活用がスムーズに進む
役職・階層・部署部門問わず、誰もがデータを参照し、分析・活用できるように環境を整える「データの民主化」が叫ばれている中、適切にデータマネジメントが行われていることは大前提です。これにより一般社員から経営層まで必要なデータの活用がスムーズに進められます。
◆迅速な意思決定につながる
データマネジメントが適切に行われている企業では、経営、部署・部門ごと、リーダーごとに求められる意思決定が迅速になります。全体として日々の業務・経営スピードが上がり、日々変化する環境に追随していくことができるでしょう。
◆データガバナンスを図ることができる
社内のガバナンスの観点において、データ領域の信頼性が向上し、セキュリティ体制を強固なものにすることができます。市場で生き残るためには優位性やスピードだけでなく、いかにリスクを避けられるかも問われています。ガバナンスの観点で適正な管理ができていることは、万が一のインシデントにも迅速に対応が可能になります。
データマネジメントを妨げるもの
企業のデータマネジメントは、単なるIT課題ではなく経営課題ですが、その推進は組織・文化・技術にまたがる根深い課題によって妨げられます。
最大の障壁は、データガバナンスの欠如です。全社的なデータ管理の方針やルール、推進体制が不在なため、データの所有者や品質に対する責任の所在が曖昧になります。結果として、各部署が独自のルールでデータを管理・蓄積し、情報が孤立する「データのサイロ化」を招きます。例えば、同じ「顧客」という言葉でも営業部門と経理部門で定義が異なるといった事態が発生し、全社横断での正確なデータ分析を著しく困難にします。
組織文化の面では、「データは自部署の資産」という縦割り意識が、部門を超えたデータ共有や連携を阻む壁となります。また、従業員のデータリテラシー不足も深刻です。データを正しく読み解き、その品質の重要性を理解し、ビジネスに活かすスキルがなければ、どれだけ優れたデータを整備しても「宝の持ち腐れ」となってしまいます。
これらの組織的・人的課題は、データ品質の低下に直結します。入力形式の不統一、重複、欠損などが放置され、信頼性の低いデータがシステムに蓄積され続けます。品質の低いデータは、AIによる需要予測やBIツールでの経営分析の精度を大きく下げ、IT投資の効果を著しく損なう原因となります。
技術面では、長年利用してきたレガシーシステムや、オンプレミスとクラウドにまたがり複雑化したデータ基盤が、迅速なデータ統合・連携を難しくし、コストや時間を増大させる「技術的負債」としてのしかかります。
これらの課題は相互に影響し合うため、ツール導入といった部分的な解決策ではなく、経営層の主導のもと、全社的な視点での包括的なアプローチが不可欠です。
データマネジメントを効率的に進めるヒント
データマネジメントを効率的に進める方法として、次のことが挙げられます。
◆データマネジメントの運用を目的にすり替えない
データマネジメントを運用していくにあたって、運用そのものを主軸に置いてしまうと、データベースの整備やデータセキュリティの強化にばかりコストやリソースを投入することになるでしょう。
その管理体制を整えることを重視しすぎると、肝心のデータ活用に不便が生じたり、スムーズな活用ができなくなったりする恐れもあります。
データマネジメントの目的は、社員や経営層がデータを活用してビジネスに役立てるための管理です。データマネジメントは目的を見失わないことがポイントといえます。
◆データ品質の向上に努める
データマネジメントの領域の一つであるデータ品質の向上はデータマネジメントの重要な側面であり、データマネジメントの運用中には特に重要です。例えば、BIツールでデータ分析基盤のベースを作り、社内データを整理し、可視化した上で社内での活用を促します。このプロセスでは、データの妥当性、完全性、一貫性、正確性、適時性を継続的にチェックし、データ品質を維持し、向上させる努力が求められます。
◆管理体制の定期的な見直し・改善
データマネジメントの活動が効果的に行われているかを定期的に見直し、改善していくことは重要です。ただシステムを導入するだけでは、実際の活用が進むことはありません。社内のニーズに応えられているのか、セキュリティは本当に保てているのか、どこかにリスクは潜んでいないかなどを随時確認していくことが重要です。
まとめ
データマネジメントはデータ活用時代に欠かせない重要な取り組みです。これから始める際には、データ活用基盤の構築から管理、運用まで、ぜひ環境づくりにも注力してください。
その過程で、ビジネスインテリジェンス(BI)や分析ツールを導入することも一つの有効な手段です。その際には、ぜひラキールの「LaKeel BI」をご利用ください。
BI(ビジネスインテリジェンス)や分析に関する知識がなくても、膨大なデータと豊富なテンプレートから様々な課題に対する解決策を複数のユーザーが探索できる分析ツール・ソフトウェアであり、データマネジメントの実行においても有用です。